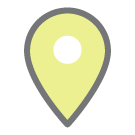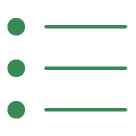賛育会病院
について


病院の理念・基本方針
理念
「隣人愛」の精神に基づいた
医療・保健活動を行い
地域社会に貢献します。
基本方針
- 東京都東部地域における急性期から慢性期までの地域密着病院としての役割をはたします。
- 「周産期・小児医療」「成人・老年期地域医療」「終末期医療」を柱としてその充実につとめます。
- 地域から信頼される病院であるよう、安全で安心な医療の提供をめざします。
患者さんの権利とお願い
1. 個人として尊重される権利
2. 良質な医療を公平に受ける権利
3. 知る権利
4. 選択の自由と自己決定の権利
6. プライバシーが守られる権利
患者の皆さまへのお願い
- ご自身の健康に関するありのままの情報の提供
- ご自身が受ける医療への積極的な参加
- 全ての患者の皆さまが適切な医療を受けるために必要な基本的ルールの遵守
セカンドオピニオンについて
院長挨拶

賛育会病院 院長
賀藤 均
すべての患者さんへ
安心の医療を。
それが私たちの使命です
2024年4月1日から院長に就任しました賀藤(かとう)と申します。私は小児科医で、東京大学医学部附属病院、国立成育医療研究センターで、小児循環器専門医として30年以上勤務し、2022年に国立成育医療研究センター病院長を定年退職後、賛育会病院に副院長として赴任しておりました。
当院の特徴は、民間病院にも関わらず規模の大きな産科、小児科・新生児科が存在していることです。これらの診療科は、墨田区だけなく隅田川以東の区部においては中心的役割を果たしています。特に小児科は、急激に進む少子化にも関わらず、小児の入院が可能な病院として重要性と希少価値が増しています。これ程の小児科の規模を持つ病院は、地方・首都圏に関わらず、非常に稀となっているのが現状です。この特徴を大きく伸ばし、隅田川以東区部の小児医療の中心的存在の地位を確立したいと思っております。また、少子化に関わらず近年増加している医療的ケア児の医療、生活支援の充実していくことも重要と考えています。
当院の歴史を見ると、1918年に「妊婦乳児相談所」を原点として、翌19年日本で最初の一般向けの産院が「本所産院」として開設されて以来、当院の産科は地域の分娩、妊産婦ケアの中心でした。ここ数年は出産数の減少の影響を受けてはいますが、古くなった産科病棟を時代に即した嗜好に合うよう整備し、昨年から開始した無痛分娩の一層の充実を図っていきます。妊産婦が安心して出産できる産科であり続けることは当院の最も重要なミッションの一つです。
これら産科・小児科のみでは地域の期待に応えることはできません。内科を中心として、この超高齢化社会への対応が求められます。高齢者の方々が安心して生活するには、急性期疾患の治療も重要ですが、それ以上にサルコペニアの悪化予防、フレイルの進行予防、要介護での生活支援が重要となります。当院は、高齢者の方々の包括的医療・サポートの充実を目指します。そのためには高齢者のCGA(包括的高齢者評価)等を応用した入退院支援を実施し、QOLの向上、再入院率の減少を目指します。
今後、重要視するのは在宅医療の充実です。現在も実施してはいますが、訪問医の増員、夜間体制を整備し、在宅でのケアを希望する患者さん達のご希望に沿うようにしたいと考えております。
賛育会病院は、今後10年間に、墨田区立花地区における新病院開設に伴う医療機能の一部移転、太平地区の古くなった建物の建替えを計画しています。そのためにも、地域の皆様のご期待に沿えるよう、安心して受けられる医療の充実に努力してまいります。